効果的なeラーニング教材制作の5つのポイント:受講者の理解度を最大化する秘訣
- Adop-Context

- 2025年9月29日
- 読了時間: 12分

「eラーニング教材を制作したのに、受講者の反応がいまひとつ...」 「研修を受けても、実際の業務で活かされていない気がする...」 「教材制作にかけた時間と費用に見合った効果が感じられない...」
企業の教育・研修にeラーニングを導入する企業が増える中、このような課題を抱える担当者は少なくありません。同じような内容でも、作り方によって学習効果に大きな差が生まれるのがeラーニング教材の特徴です。
今回は、数多くの業界で教材制作を手がけた経験から見えてきた、受講者の理解度を最大化するための5つのポイントをご紹介します。
eラーニング教材制作でよくある3つの失敗
まず、効果的な教材を作るために避けるべき、よくある失敗パターンを確認しましょう。
失敗①:従来の集合研修をそのまま動画化する間違い
最も多い失敗が、これまで行っていた集合研修の内容をそのまま動画に撮影しただけの教材です。講師が一方的に話している様子を録画しただけでは、受講者は受動的な学習になってしまい、集中力も続きません。
eラーニングには eラーニング特有の効果的な構成や演出があります。対面研修とは全く異なるアプローチが必要なのです。
失敗②:一方通行の説明だけで終わってしまう内容
「○○とは何か」「○○の方法」といった知識の説明だけで構成された教材も、学習効果が限定的です。知識を覚えることはできても、実際の業務でどう活用するかがイメージできず、行動変容につながりません。
特に大人の学習では、「なぜ必要なのか」「どう活用するのか」が明確でないと、学習意欲も継続しません。
失敗③:受講者の実際の業務や状況を考慮しない画一的な教材
一般的な内容だけで構成された教材は、受講者にとって「他人事」に感じられがちです。自分の業務や職場環境と結びつけて考えることができず、学習内容が定着しません。
受講者が「自分の場合はどうだろう?」と考えられる具体性と関連性が重要です。
効果的なeラーニング教材制作の5つのポイント
これらの失敗を避け、真に効果的な教材を制作するための5つのポイントをご紹介します。
ポイント①:受講者の背景と目的を徹底的に理解する
効果的な教材制作の第一歩は、受講者を深く理解することです。
具体的に把握すべき項目:
対象者のレベル: 初心者なのか、ある程度経験があるのか
業務背景: どのような仕事をしており、どんな課題を抱えているか
学習環境: いつ、どこで、どのような環境で受講するのか
学習動機: なぜこの教育を受ける必要があるのか
これらを詳細に分析することで、受講者にとって本当に価値のある学習内容を設計できます。
「なぜこの教育が必要なのか」の明確化
受講者が学習に取り組む動機を高めるために、冒頭で「なぜこの学習が重要なのか」「学習後にどのような変化が期待できるのか」を具体的に示すことが重要です。
ポイント②:「体感できる」コンテンツ設計
知識の伝達だけでなく、受講者が「体感」できるコンテンツにすることで、学習効果は飛躍的に向上します。
実際の業務シーンを再現した映像活用
抽象的な説明よりも、実際の職場で起こりうるシーンを映像で再現することで、受講者は自分の業務と重ね合わせて学習できます。
役者を起用した再現ドラマの効果
特に効果的なのが、プロの役者を起用した再現ドラマです。リアルな演技により、受講者は感情的にも内容を理解し、記憶に残りやすくなります。良い例と悪い例を対比で見せることで、違いが明確になり、「なるほど!」という気づきを生み出せます。
受講者が「自分事」として捉えられる具体的なストーリー
一般論ではなく、受講者の業界や職種に特化した具体的なストーリーを用いることで、「まさに自分の職場でも同じことが起きている」と感じてもらえます。
ポイント③:能動的な学習を促すインタラクティブ要素
受講者が受動的に視聴するだけでなく、能動的に参加できる仕組みを取り入れることが重要です。
単純視聴から参加型学習への転換
動画を見るだけではなく、途中でクイズや質問を挟んだり、受講者自身に考えてもらう時間を設けることで、集中力を維持し、理解度を深めることができます。
ケーススタディを活用した討議形式
実際の事例を題材に、「この場合、あなたならどうしますか?」といった問いかけを行い、受講者同士で討議できるような構成にすると、より深い学習が期待できます。
受講者同士の議論を促進する仕組み
特に効果的なのは、映像視聴後に職場のメンバーで討議する時間を設けることです。それぞれの視点や経験を共有することで、一人では気づけなかった新たな発見が生まれます。
ポイント④:業界・職種特性に応じたカスタマイズ
画一的な内容ではなく、対象となる業界や職種の特性に応じてカスタマイズすることで、教材の価値は大幅に向上します。
多様な分野への対応実績
これまでに手がけた教材制作の実績から、業界ごとの特徴をご紹介します:
EAP事業者向け: 相談者の心理状態に配慮した対応スキルの習得
ソフトウェア会社向け: 複雑な操作手順を分かりやすく伝えるチュートリアル
大手金融向け: 実際の業務で遭遇するケースを題材にした実践的な学習
規定集の教材化: 堅い内容も親しみやすく、理解しやすい形に変換
食育・健康分野: 日常生活に取り入れやすい実践的なコンテンツ
それぞれの分野に最適化された表現方法
同じ「コミュニケーション」をテーマにしても、営業職と医療従事者では求められるスキルが異なります。受講者の職種や業務内容に応じて、事例や表現方法を最適化することが重要です。
ポイント⑤:継続的な気づきと実践を促す構成
一度の受講で終わりではなく、継続的な学習と実践を促す仕組みを組み込むことが大切です。
一度の受講で終わらない学習設計
学習内容を段階的に提供したり、定期的な復習コンテンツを用意することで、知識とスキルの定着を図ります。
現場での実践にすぐ活かせる具体性
「明日から使える」具体的なスキルやノウハウを提供することで、受講者は学習内容を実際の業務で試してみようという意欲を持てます。
継続的な行動変容を支援する仕組み
学習後のフォローアップ体制や、実践結果を共有できる場を設けることで、一時的な学習ではなく、継続的な行動変容を支援できます。
成功事例:映像を活用した体感型学習の効果
実際に効果的な教材制作で成果を上げた事例をご紹介します。
【事例:接客力向上のための映像研修】
Before:従来の座学研修では理論的な理解にとどまる ある企業では、従来の座学形式での接客研修を実施していましたが、受講者は理論的な理解はできても、実際の接客場面での応用が難しい状況でした。「接客の基本は理解したが、実際のお客様を前にすると、どう対応すればよいか分からない」という声が多く聞かれていました。
制作アプローチ:体感できる映像教材の開発
この課題を解決するため、以下のアプローチで教材を制作しました:
役者を起用した実際の接客シーンの再現ドラマ プロの役者に、実際の接客現場で起こりうる様々なシーンを演じてもらいました。お客様役も役者が演じることで、リアルな感情表現や反応を再現できました。
良い例・悪い例を対比で表現 同じ状況で「適切な対応」と「不適切な対応」を対比して見せることで、違いが明確になり、「なぜその対応が良いのか(悪いのか)」が直感的に理解できるようになりました。
視聴後の討議を前提とした構成設計 映像を見て終わりではなく、職場のメンバーで「自分たちの職場ではどうか?」「同じような経験はないか?」を討議できるような構成にしました。
After:従業員同士での議論が活発化し、現場での実践に直結
この映像研修の導入により、以下の効果が得られました:
従業員同士での議論が活発化:映像を見た後、「あのシーンは自分も経験した」「もっと良い方法があるのでは?」といった討議が自然に始まるようになりました。
これまで気づかなかった課題や改善点が明確に:映像によって客観的に接客シーンを見ることで、普段は気づかない自分たちの課題や改善点を発見できるようになりました。
現場での実践にすぐに活用:具体的な接客シーンを見ることで、「明日からこの方法を試してみよう」という実践意欲が高まり、実際の業務改善につながりました。
【多様な業界での実践例】
この体感型アプローチは、様々な業界で効果を発揮しています:
EAP事業者:相談対応スキル向上 相談者の微妙な心理状態や感情の変化を、役者の演技で
細かく表現。相談対応者が「この表情の時は、こんな気持ちなのか」と体感的に理解できるようになりました。
ソフトウェア会社:操作チュートリアル 単純な画面操作説明ではなく、「なぜその操作が必要なのか」「間違えやすいポイントはどこか」をストーリー仕立てで解説。ユーザーの習得速度が大幅に向上しました。
大手金融:ケーススタディ 複雑な金融商品の説明を、お客様とのやり取りの再現ドラマで表現。担当者が顧客視点で商品を理解し、より適切な提案ができるようになりました。
効果的な教材制作の実践プロセス
効果的な教材を制作するための具体的なプロセスをご紹介します。
企画段階:ニーズの深掘りと学習設計
受講者へのヒアリングと現場観察
教材制作前に、実際の受講者や現場担当者から詳しく話を聞くことが重要です。「どんな場面で困っているか」「どんなスキルがあれば助かるか」を具体的に把握します。
学習目標の具体化と測定方法の設定 「○○について理解する」といった抽象的な目標ではなく、「○○の場面で、××の対応ができるようになる」という具体的で測定可能な目標を設定します。
最適な教材形式の選択 内容や目的に応じて、映像教材、対面研修、オンライン学習、あるいはそれらを組み合わせたハイブリッド形式など、最適な手法を選択します。
制作段階:目的に応じた最適な手法選択
再現ドラマ、インタビュー、講義形式の使い分け
再現ドラマ: 実際の業務シーンを体感してもらいたい場合
インタビュー: 経験者の生の声や体験談を伝えたい場合
講義形式: 体系的な知識を効率よく伝えたい場合
受講者が集中できる構成と時間設定
一つのコンテンツは10〜15分程度に区切り、適度に質問やクイズを挟むことで、集中力を維持できるように構成します。
視覚的・聴覚的要素の効果的な組み合わせ
図表やイラスト、音楽、効果音なども適切に活用し、受講者の五感に働きかける教材にします。
運用段階:学習効果の最大化
受講環境の整備と推進体制の構築
教材を作っただけでは効果は限定的です。受講しやすい環境づくりや、管理職による推進体制の構築も重要です。
受講後の実践支援とフォローアップ
学習内容を実際の業務で活用できるよう、受講後のサポート体制を整えます。質問対応や実践事例の共有なども効果的です。
効果測定と教材の継続改善
受講者のフィードバックや実際の業務への活用状況を継続的に収集し、教材の改善に活かします。
内製化 vs 専門パートナー活用の判断基準
効果的な教材制作を実現するために、内製化と外部委託のどちらを選ぶべきかは重要な判断ポイントです。
内製化が向いているケース
社内にスキルとリソースが十分にある場合
映像制作や教材開発の経験者がいる
継続的に教材制作のニーズがある
時間的余裕が十分にある
社内情報の機密性が重要な場合
外部に出せない機密情報を含む内容
社内でしか分からない業務の詳細な手順
専門パートナー活用が効果的なケース
高品質な教材が必要な場合
役者を起用したプロフェッショナルな映像が必要
多くの受講者に長期間使用される重要な教材
企業の信頼性に関わる対外的な教材
短期間での制作が必要な場合
急な研修ニーズへの対応
法改正や制度変更への迅速な対応
客観的な視点での教材設計が重要な場合
社内の常識に捉われない第三者視点が必要
受講者の立場に立った客観的な評価が必要
専門的なスキルが必要な場合
映像撮影・編集の技術的品質
教育効果を最大化する学習設計
様々な業界での制作経験に基づくノウハウ
ハイブリッド型アプローチの提案
最も効果的なのは、内製化と外部委託を組み合わせたハイブリッド型のアプローチです:
企画・設計: 外部の専門知識を活用
素材提供: 社内の業務知識を活用
制作・編集: 外部の技術力を活用
運用・改善: 社内での継続的な取り組み
このように役割分担することで、品質と効率性を両立できます。
まとめ:受講者中心の教材制作で学習効果を最大化
効果的なeラーニング教材制作の鍵は、「受講者中心」の発想に立つことです。制作者の視点ではなく、学ぶ人の立場に立って教材を設計することで、真に価値のある学習体験を提供できます。
「体感できる」コンテンツの価値
特に重要なのは、受講者が「体感」できるコンテンツにすることです。役者を起用した再現ドラマや具体的なケーススタディにより、知識の暗記ではなく、実践的なスキルの習得を促進できます。
多様な業界・職種への柔軟な対応
EAPから金融、ソフトウェア、食育まで、様々な分野での制作経験により、それぞれの業界特性に応じた最適な教材を提供できます。画一的なアプローチではなく、受講者のニーズに合わせたカスタマイズが学習効果を大幅に向上させます。
継続的改善による長期的価値
教材制作は一度作って終わりではありません。受講者の反応や実際の業務での活用状況をフィードバックとして収集し、継続的に改善することで、長期にわたって価値を提供し続けることができます。
効果的なeラーニング教材制作をサポートします
「受講者に本当に身につく教材を作りたい」「映像を活用した体感型の教材に興味がある」「業界特性に応じたカスタマイズ教材が必要」など、教材制作に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
動画制作からオンサイト研修まで、ニーズに応じた最適な教育ソリューションをご提案いたします。受講者の理解度を最大化する教材制作で、貴社の人材育成を成功に導きます。
まずは現在の教育課題をお聞かせください。効果的な解決策をご提案いたします。


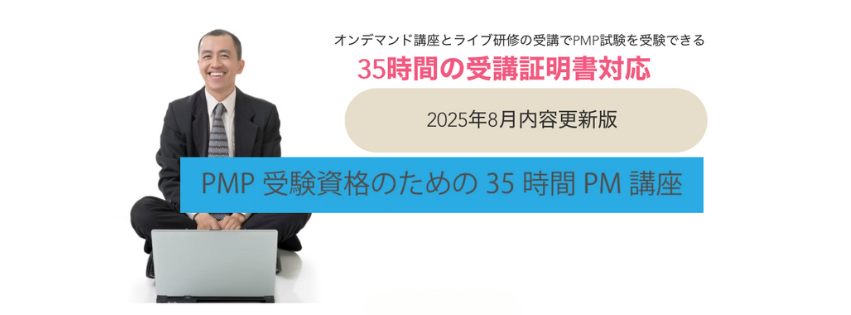


コメント