社員が続かないeラーニング、改善の鍵は「集中力」と「実践力」にあり
- Adop-Context

- 2023年5月21日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月17日

せっかく導入したeラーニング、社員が最後までやり切れていない。
そんな課題を感じていませんか?
近年、eラーニングは「動画学習」「マイクロラーニング」などの言葉に置き換わりながらも、企業研修の主要な手法として定着しています。とはいえ、「見ただけ」で終わる学びになってしまっているケースも多く、教育担当者としては頭を悩ませるポイントです。
本記事では、eラーニングでの集中力を高め、スキルアップにつなげるための実践的な方法をご紹介します。
1. 集中力を維持する3つのポイント
在宅でも、業務の合間でも、効果的な学びを継続するために
(1)学習の「時間」と「場所」を固定する
社員が自発的に学ぶには、ルーティン化が効果的です。
毎朝の業務前15分を「インプットタイム」に
昼休み後の15分は「復習タイム」に
スキマ時間に少しずつではなく、「この時間は学習に集中する」と決めることで、学びに向き合う姿勢が変わります。
(2)通知を遮断する「デジタルデトックス」
集中を阻害する最大の敵は、スマートフォンと通知。
学習中はスマホを別室に置く
PCのチャット通知は一時停止
物理的・心理的に「邪魔の入らない空間」をつくることで、短時間でも質の高い学習が実現します。
(3)「見た目の進捗」がモチベーションに
eラーニングの学習画面に進捗バーや達成バッジがある場合、積極的に活用を促しましょう。達成感が継続のモチベーションにつながります。
2. スキルアップを実感するための工夫
「見るだけ」から「使える知識」へ
(1)業務と連動した「アウトプット設計」
動画を見るだけでは、定着しません。
視聴後に「業務でどこに活かせるか」を自己記入
小さな実践タスクを設けて、社内チャットで共有
実務と結びつけることで、「知っている」から「できる」へと変わります。
(2)「忘れさせない」復習サイクルを仕組み化
人は1回学んだだけでは忘れてしまいます。
1週間後に3分クイズで内容を再確認
1ヶ月後にケーススタディで応用演習
このような復習のリマインド設計は、学びの定着率を大きく高めます。
(3)第三者からのフィードバックを取り入れる
スキルは、他者の視点で見直すことではじめて磨かれます。
上司やOJT担当からの簡易コメント
チーム内での成果共有とフィードバック会
「気づき→実践→評価」の循環を仕組みとして回せば、研修効果が見える化され、教育のPDCAも回しやすくなります。
まとめ:集中と実践が、eラーニングを"成果"に変える
eラーニングはただ導入するだけでは効果が見込めません。「どう学ぶか」「どう使うか」を設計しなければ、研修効果は見えにくいものです。
人事・教育担当としては、受講者が「集中して学べる仕組み」と「実践につながる学び」を提供することが求められます。本記事の内容を取り入れて、自律的に学び、行動できる人材育成を進めていきましょう。


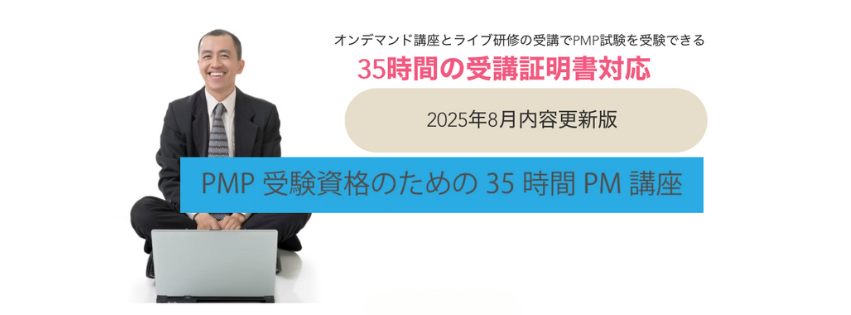


コメント