テレワーク時の効果的なチームワークとその推進方法
- Adop-Context

- 2023年7月12日
- 読了時間: 15分
更新日:2025年8月26日

はじめに:テレワークが突きつける新たな組織課題と人事の役割
近年、働き方の多様化が急速に進み、テレワークはもはや特別な働き方ではなく、多くの企業で標準的な選択肢となっています。しかし、この変化は単に働く場所が変わるだけでなく、組織運営、特に「チームワーク」のあり方に根本的な問いを投げかけています。オフィスという物理的な空間を共有しない環境で、いかにして従業員間の連携を深め、生産性を維持・向上させ、そして企業文化を醸成していくのか。これは、人事担当者の皆様が今、最も頭を悩ませている課題の一つではないでしょうか。
かつて、チームワークは自然発生的に育まれるものと捉えられがちでした。同じ空間で顔を合わせ、偶発的な会話から生まれるアイデアや、非言語的なコミュニケーションがチームの結束を強めていた側面は否定できません。
しかし、テレワーク環境下では、これらの要素が希薄になりがちです。結果として、従業員エンゲージメントの低下、チーム間のサイロ化、新入社員のオンボーディングの難しさ、そして最終的には生産性の停滞や離職率の増加といった、看過できない組織課題が顕在化しています。
本記事では、人事担当者の皆様が直面するこれらの課題に対し、テレワーク時代に真に機能するチームワークを構築するための具体的な戦略と実践方法を深く掘り下げていきます。単なるコミュニケーションツールの紹介に留まらず、組織全体の生産性向上、従業員満足度の向上、ひいては企業の持続的成長に貢献する「攻めの人事戦略」としてのチームワーク推進について、実践的な視点から解説します。貴社の組織を次なるステージへと導くためのヒントが、ここにあります。
1: テレワークにおけるチームワークの現状と課題:人事担当者が直視すべき現実
従来のオフィス環境では、チームワークは自然な形で育まれることが期待されていました。同じ空間で働くことで、メンバー間の偶発的な交流が生まれ、非言語的な情報交換が円滑な連携を促進していました。しかし、テレワークへの移行は、この「自然発生的なチームワーク」の基盤を大きく揺るがしました。人事担当者の皆様は、この変化が組織にもたらす具体的な課題を正確に把握し、対応していく必要があります。
1.1. コミュニケーションの質の低下とサイロ化
テレワーク環境下では、コミュニケーションの主な手段がテキストベースのチャットやメール、そしてオンライン会議に限定されます。これにより、以下のような問題が生じやすくなります。
• 情報の意図の誤解: テキストのみでは、言葉のニュアンスや感情が伝わりにくく、誤解が生じやすくなります。これにより、認識の齟齬から業務のやり直しや無駄な時間が発生する可能性があります。
• 偶発的なコミュニケーションの減少: オフィスでの「ちょっとした声かけ」や「休憩室での雑談」といった偶発的なコミュニケーションは、チーム内の情報共有やアイデア創出に大きく貢献していました。テレワークではこれが失われ、部門間やチーム間の連携が希薄になり、組織全体のサイロ化を招く恐れがあります。
• 心理的安全性の低下: メンバーが気軽に質問したり、意見を述べたりできる心理的安全性が確保されにくい環境では、問題が表面化しにくく、イノベーションが阻害される可能性があります。
1.2. 従業員エンゲージメントの低下と孤立感
物理的な距離は、精神的な距離にも繋がりかねません。テレワークが長期化するにつれて、従業員は以下のような課題に直面しやすくなります。
• 帰属意識の希薄化: 会社やチームとの物理的な接点が減少することで、組織への帰属意識が薄れ、エンゲージメントが低下するリスクがあります。特に新入社員や中途入社者にとっては、組織に馴染む機会が限られ、孤立感を抱きやすくなります。
• モチベーションの維持困難: 周囲のメンバーの働きが見えにくい環境では、自身の貢献が正当に評価されているか不安を感じたり、モチベーションを維持しにくくなったりすることがあります。
• ワークライフバランスの崩壊: 自宅が職場となることで、仕事とプライベートの境界線が曖昧になり、長時間労働や燃え尽き症候群に繋がるケースも報告されています。
1.3. 人材育成と評価の難しさ
テレワークは、従来のOJT(On-the-Job Training)や人事評価のあり方にも影響を与えています。
• OJTの形骸化: 上司や先輩が部下の業務状況を直接把握しにくくなるため、きめ細やかな指導やフィードバックが難しくなります。これにより、特に若手社員の成長機会が失われる可能性があります。
• 公平な評価の困難: 成果だけでなく、プロセスやチームへの貢献度を評価することが難しくなります。これにより、評価の公平性に対する不満が生じ、従業員の不信感に繋がる恐れがあります。
• マネジメント層の負担増大: テレワーク環境下でのチームマネジメントは、メンバーの状況把握、目標設定、進捗管理、モチベーション維持など、マネージャーに新たなスキルと負担を要求します。
これらの課題は、単に個々の従業員の問題に留まらず、組織全体の生産性低下、離職率の増加、そして企業の競争力低下に直結する深刻な問題です。人事担当者の皆様には、これらの現状を深く理解し、積極的な対策を講じることが求められています。
2: 人事担当者が推進すべきテレワーク時代のチームビルディング戦略
テレワーク環境下でのチームワークの課題を認識した上で、人事担当者の皆様には、これらの課題を克服し、むしろテレワークの利点を最大限に活かすための戦略的なチームビルディングを推進することが求められます。ここでは、具体的な施策を4つの柱に分けて解説します。
2.1. 戦略1: コミュニケーションの質と量を高める施策
テレワークにおけるコミュニケーションは、意図的に設計され、実行される必要があります。単にツールを導入するだけでなく、その活用方法や文化を醸成することが重要です。
• ツールの選定と活用法の徹底:
• チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど): リアルタイムでの情報共有、気軽な質問、雑談の場として活用を促します。絵文字やスタンプの使用を推奨し、心理的なハードルを下げる工夫も有効です。
• ビデオ会議ツール(Zoom, Google Meetなど): 定期的なチームミーティングはもちろん、1on1ミーティング、朝礼・終礼など、顔を合わせて話す機会を意識的に設けます。背景設定やバーチャル背景の使用を許可するなど、参加しやすい環境を整えることも大切です。
• プロジェクト管理ツール(Asana, Trello, Jiraなど): 誰が何を、いつまでに、どのような状況で進めているのかを可視化し、情報共有の漏れを防ぎます。これにより、メンバー間の連携をスムーズにし、進捗管理の効率化を図ります。
• オンラインホワイトボードツール(Miro, Muralなど): アイデア出しやブレインストーミング、ワークショップなど、共同作業が必要な場面で活用します。視覚的に情報を共有することで、理解度を深め、議論を活性化させます。
• 非同期コミュニケーションの最適化:
• すべてのコミュニケーションをリアルタイムで行う必要はありません。非同期コミュニケーション(メール、チャット、ドキュメント共有など)を効果的に活用することで、各自のペースで業務を進めつつ、必要な情報を共有できます。重要なのは、情報の意図を明確に伝えるための「書き方」のルールを定めることです。例えば、「目的」「背景」「結論」「次のアクション」を明記するテンプレートの使用を推奨するなどです。
• 雑談の機会創出と心理的安全性の確保:
• 「バーチャルコーヒーブレイク」や「オンラインランチ会」など、業務とは関係ない雑談の時間を設けることで、メンバー間の人間関係を構築し、心理的安全性を高めます。また、週に一度の「フリートークタイム」を設けたり、特定のテーマについて語り合うチャンネルを作成したりすることも有効です。マネージャーは、メンバーが安心して意見を言える雰囲気作りを意識的に行う必要があります。
2.2. 戦略2: 役割と目標の明確化、評価制度の再構築
テレワーク環境下では、個々のメンバーの自律性が求められる一方で、チームとしての方向性を明確にすることが不可欠です。また、成果を公正に評価する仕組みも重要になります。
• OKR(Objectives and Key Results)やMBO(Management by Objectives)など目標管理手法の活用:
• チームおよび個人の目標を明確にし、その達成度を定期的に確認する仕組みを導入します。目標を共有することで、メンバーは自身の役割と貢献を認識しやすくなり、自律的な行動を促します。目標設定の際には、SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に基づき、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。
• パフォーマンス評価の透明化とフィードバックの重要性:
• テレワークでは、プロセスが見えにくくなるため、成果に基づいた評価がより重要になります。評価基準を明確にし、評価プロセスを透明化することで、従業員の納得感を高めます。また、定期的な1on1ミーティングを通じて、成果だけでなく、業務遂行における課題や成長ポイントについて具体的にフィードバックを行うことが不可欠です。ポジティブなフィードバックと改善点の両方をバランス良く伝えることで、メンバーの成長を支援します。
2.3. 戦略3: 人材育成とエンゲージメント向上施策
テレワーク下でも従業員の成長を支援し、高いエンゲージメントを維持することは、組織の持続的成長に直結します。
• オンラインOJT、メンター制度の導入:
• 従来のOJTが難しい場合、オンラインでのOJTプログラムを開発します。例えば、画面共有を活用した実務指導、録画された研修動画の活用、チャットツールでのリアルタイムサポートなどが考えられます。また、新入社員や若手社員に対してメンターを配置し、定期的なオンライン面談を通じて業務の相談だけでなく、キャリア形成やメンタルヘルスに関するサポートを提供します。
• eラーニング、ウェビナーの活用:
• 時間や場所にとらわれずに学習できるeラーニングシステムを導入し、従業員のスキルアップを支援します。また、社内講師によるウェビナーや外部講師を招いたオンライン研修を定期的に開催し、専門知識の習得や最新情報の共有を促進します。これにより、従業員の学習意欲を高め、自律的な成長を促します。
• 従業員満足度調査、パルスサーベイの実施:
• 定期的に従業員満足度調査やパルスサーベイ(短期間で頻繁に行う簡易アンケート)を実施し、従業員のエンゲージメントや心理状態を把握します。これにより、早期に課題を発見し、適切な対策を講じることが可能になります。匿名性を確保することで、従業員が安心して本音を伝えられる環境を整えることが重要です。
2.4. 戦略4: 企業文化の醸成と浸透
テレワーク環境下でも、企業独自の文化を維持・発展させることは、組織の一体感を醸成し、従業員のエンゲージメントを高める上で不可欠です。
• ビジョン・ミッションの共有と浸透:
• 企業のビジョンやミッション、バリューを定期的に共有し、それが日々の業務にどのように結びついているかを具体的に示すことで、従業員の共感を促します。オンラインでの全社集会や、社内報、イントラネットなどを活用し、メッセージを繰り返し発信することが重要です。
• オンラインイベント、社内交流の促進:
• 忘年会や歓迎会といったイベントをオンラインで開催したり、部署横断のオンライン交流会を企画したりすることで、従業員間の非公式な交流を促進します。オンラインゲーム大会やオンライン飲み会など、カジュアルなイベントも有効です。これにより、従業員同士の絆を深め、一体感を醸成します。
これらの戦略を複合的に実施することで、人事担当者の皆様は、テレワーク環境下においても強固なチームワークを構築し、組織全体のパフォーマンスを最大化することが可能になります。
3: 成功事例に学ぶ!テレワークでチームワークを強化した企業
理論だけでは、具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、実際にテレワーク環境下でチームワークを強化し、成果を出している企業の事例をいくつかご紹介します。これらの事例から、貴社に適用可能なヒントを見つけていただければ幸いです。
ケース1: コミュニケーションの「量」と「質」を両立させたIT企業A社
IT企業A社は、コロナ禍以前から一部テレワークを導入していましたが、全面移行に伴い、コミュニケーション不足による連携ミスや従業員の孤立感が課題となっていました。そこで人事部が主導し、以下の施策を導入しました。
• ツール活用ルールの徹底: Slackのチャンネルを細分化し、業務連絡用、雑談用、趣味用など明確な目的を設定。各チャンネルでの発言ルール(例: 業務連絡は簡潔に、雑談は絵文字活用推奨)を設け、コミュニケーションの質を向上させました。
• 「バーチャルオフィス」の導入: 常に接続されているオンライン会議室を「バーチャルオフィス」として開放。メンバーは自由に出入りし、画面共有しながら共同作業を行ったり、休憩時間に雑談したりすることで、偶発的なコミュニケーションを創出しました。
• 週次「チームランチ」: 毎週金曜日のランチタイムに、チームごとにオンラインで集まり、業務以外の話題で交流する時間を設けました。会社からランチ代の一部補助を出すことで参加を促し、メンバー間の親睦を深めました。
結果: 導入後6ヶ月で、従業員エンゲージメントサーベイの「チームとの連携」に関する項目が15%向上。プロジェクトの遅延も減少し、生産性向上に寄与しました。
ケース2: 目標管理とフィードバックで自律性を育んだ製造業B社
伝統的な製造業であるB社は、テレワーク導入により、マネージャーが部下の業務状況を把握しにくいという課題に直面していました。そこで、人事部と連携し、OKR(Objectives and Key Results)を全社的に導入し、評価制度を見直しました。
• OKRの導入と運用: 四半期ごとにチームと個人のOKRを設定。目標は全社に公開され、進捗状況もリアルタイムで共有される仕組みを構築しました。これにより、メンバーは自身の業務が全体の目標にどう貢献しているかを常に意識できるようになりました。
• 「成果」と「プロセス」の可視化: 各メンバーは日々の業務日報をオンラインツールで共有し、週次でマネージャーと1on1ミーティングを実施。ミーティングでは、OKRの進捗だけでなく、業務プロセスにおける課題や成功体験、個人の成長について深く議論する時間を設けました。これにより、マネージャーは部下の状況を詳細に把握し、適切なフィードバックを提供できるようになりました。
• 多面評価の導入: 上司だけでなく、同僚や部下からのフィードバックも評価に反映する多面評価制度を導入。これにより、テレワーク下で見えにくい「チームへの貢献度」や「協調性」といった側面も評価対象となり、評価の公平性が向上しました。
結果: OKR導入後1年で、従業員の目標達成意識が向上し、自律的な業務遂行能力が向上。また、マネージャーのマネジメント負担も軽減され、評価に対する従業員の納得度も高まりました。
ケース3: 人材育成と企業文化をオンラインで醸成したサービス業C社
サービス業C社は、新入社員のオンボーディングと企業文化の浸透がテレワークで困難になることを懸念していました。そこで、オンラインに特化した人材育成プログラムと交流イベントを企画しました。
• オンラインオンボーディングプログラム: 新入社員向けに、会社の歴史、ビジョン、各部署の役割などを学ぶeラーニングコンテンツを充実させました。また、配属部署の先輩社員がメンターとなり、毎日オンラインでチェックインする制度を導入。これにより、新入社員は早期に会社に馴染み、業務に必要な知識を習得できました。
• 「オンライン部活動」の奨励: 趣味の合う社員同士がオンラインで交流できる「部活動」を会社が支援。オンラインゲーム部、読書部、料理部など、多様な部活動が生まれ、業務外での交流が活発化しました。これにより、部署や役職を超えた横の繋がりが強化され、企業文化の醸成に貢献しました。
• 全社オンラインイベントの定期開催: 月に一度、全社員が参加するオンラインイベントを開催。社長からのメッセージ、部署紹介、社員表彰、クイズ大会など、様々なコンテンツを盛り込み、全社の一体感を高めました。
結果: オンラインオンボーディングプログラム導入後、新入社員の定着率が向上。また、オンライン部活動やイベントを通じて、社員間のコミュニケーションが活性化し、企業文化への共感が深まりました。
これらのケースは、業種や規模に関わらず、人事担当者の皆様が主体的に戦略を立て、実行することで、テレワーク環境下でも強力なチームワークを築き、組織の成長を加速できることを示しています。重要なのは、自社の課題を正確に把握し、既存の枠にとらわれずに最適な施策を柔軟に導入していくことです。
まとめ:テレワーク時代のチームワークは「攻めの人事戦略」の要
本記事では、テレワークがもたらす組織課題、特にチームワークの変容に焦点を当て、人事担当者の皆様が取るべき具体的な戦略と実践方法、そして成功事例をご紹介しました。
2年前のブログ記事が指摘していた「テレワークにおけるチームワークの重要性」は、今日においてさらにその重みを増しています。しかし、単に「重要である」と認識するだけでは不十分です。人事担当者の皆様には、以下の点を強くお伝えしたいと思います。
チームワークは自然発生しない、意図的な設計が必要: テレワーク環境下では、従来のオフィスで自然に生まれていたコミュニケーションや連携が失われがちです。だからこそ、コミュニケーションの仕組み、目標設定、評価、人材育成、文化醸成といったあらゆる側面において、意図的かつ戦略的にチームワークを設計し、推進していく必要があります。
人事部門が変革のドライバーとなる: テレワークにおけるチームワークの課題は、従業員個人の問題ではなく、組織全体の問題です。この変革をリードし、具体的な施策を立案・実行していくのは、まさに人事部門の重要な役割です。経営層や各部署のマネージャーと連携し、全社的な取り組みとして推進していくことが成功の鍵となります。
データに基づいたPDCAサイクル: 施策を導入したら終わりではありません。従業員エンゲージメントサーベイやパルスサーベイ、各種ツールの利用状況データなどを活用し、効果を測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが不可欠です。
テレワークにおける効果的なチームワークの推進は、単に業務を円滑にするだけでなく、従業員エンゲージメントの向上、生産性の最大化、優秀な人材の確保と定着、そして企業の持続的な成長に直結する「攻めの人事戦略」そのものです。今こそ、貴社の人事戦略の中心に「テレワーク時代のチームワーク」を据え、未来の組織をデザインしていく時です。
このブログ記事が、人事担当者の皆様が直面する課題解決の一助となり、貴社の組織がテレワーク時代においても強く、しなやかに成長していくための一歩となることを心より願っています。



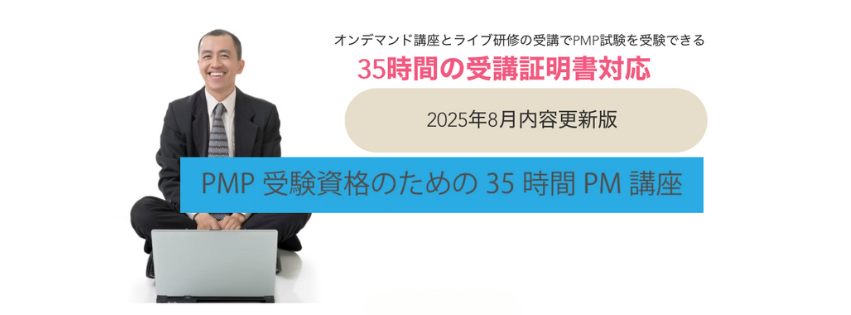

コメント