部門長・教育担当者必見!「成功への道筋」は、「対話」から生まれる~組織力を高める交渉と傾聴の新視点
- Adop-Context

- 2023年6月27日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年9月3日

日々の業務において、私たちは無意識のうちに「交渉」という行為を繰り返しています。それは、単に大規模な商談だけを指すのではありません。例えば、ミーティングの日時を調整したり、チーム内の課題解決に向けて意見を擦り合わせたり、メンバーの業務スケジュールを進める方法を提案したり、これらすべてが、まさに「提供するものとその対価となるものの提供を受けることへの合意を求めるプロセス」、つまり交渉なのです。
しかし、「一方的に自分の意見を押し通す」ような姿勢では、真の合意には至りません。部下との対話、他部署との連携、研修プログラムの選定においても、「お互いの満足を追求する」ことで、よりスムーズな協力体制が築けるのです。
では、なぜ私たちの交渉は、時にうまくいかないのでしょうか?そして、どうすれば「成果を生む対話」へと変えられるのでしょうか?
「聞く」を超えた「傾聴」が、組織の課題を浮き彫りにする
成功する交渉とは、単に自分の立場を相手に理解してもらうことではありません。「相手のニーズや課題を正確に理解し、対応すること」が不可欠です。これを実現するために、何よりも重要なスキルが「傾聴」です。
「傾聴」とは、ただ相手の話を聞き流すことではありません。冷静かつ正確に相手の要求や考えを把握するために、話を注意深く聞くことが求められます。部下のモチベーションが上がらない、部署間の連携がうまくいかない、といった課題の背景には、言葉に出されない真のニーズや状況が隠れていることが多々あります。
例えば、部下から上がってきた表面的な要望の裏にある「仕事への不安」や「成長への意欲」、あるいは研修担当者様が感じている「既存の研修プログラムでは響かない」という課題の根底にある「組織文化とスキルのギャップ」など、「言葉には出てこない背景や状況、理由」を理解しようとすることが重要です。
部門長・教育担当者様のための「質問の技術」
この深層にあるニーズを探り当てるために、「質問の技術」が不可欠となります。適切な質問を投げかけることで、相手が抱える「真のニーズ」を明らかにすることができ、双方が納得できる解決策を共に見つけやすくなります。これにより、以下のような具体的な成果が期待できます。
• 部下との信頼関係構築: 相手に対する関心と共感を示し、話しやすい環境を作ることで、部下の自律的な成長を促します。
• 部署間の連携強化: 相手部署の立場や目的を深く理解し、部門全体の生産性と効率性を向上させる合意形成が可能になります。
• 効果的な研修企画: 受講者の隠れたニーズを引き出し、真に役立つ「身に付く、課題が解決できる教育」 の設計へと繋がります。
この能力は、社員一人ひとりが持つべき重要なスキルであり、個々の仕事だけでなく組織全体の生産性と効率性を向上させるための鍵となります。
対話力を組織の強みへ:その実践のために
本記事でご紹介した「交渉と傾聴」のスキルは、日々の業務における合意形成だけでなく、組織全体の生産性と効率性を向上させる鍵となります。特に、部下を持つ部門長の方々や、組織の成長を担う教育研修担当者の方々にとって、これらのヒューマンスキルの強化は、単なる個人の能力向上に留まらず、チームのエンゲージメントや協調性を高める上で極めて重要な要素です。
こうしたスキルを組織に深く根付かせ、具体的な成果へと繋げるためには、実践的な学習機会が不可欠です。
もし、貴社組織の「対話力」をさらに高め、それが生産性やエンゲージメントの向上に繋がるとお考えでしたら、ぜひ一度、私たちの提供するサービスや考え方に触れてみてはいかがでしょうか。「なるほど、こういう交渉と傾聴の考え方があったのか」と共感いただけたなら、その気づきを、貴社の次の成長の一歩に繋げるきっかけとなれば幸いです。


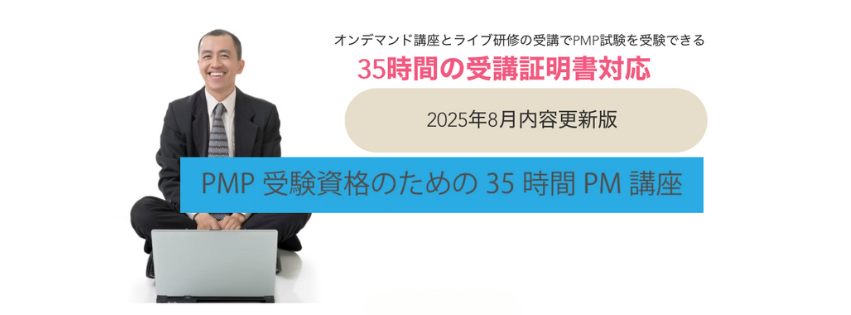


コメント