「決める力」が組織の推進力になる
- Adop-Context

- 2023年6月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年8月26日
― 決断の質を高めたいと思ったときに ―

日々の業務のなかで、私たちは気づかぬうちに多くの「決断」をしています。しかし、ふと立ち止まって考えてみると
会議で結論がなかなか出ない
上司の判断待ちが常態化している
優先順位が曖昧で動けない人が増えている
こんな“決められない職場”になってはいないでしょうか。
実は「決断力」は、生まれつきの才能ではありません。考え方を知り、手順を踏み、実践を通じて鍛えることができるスキルです。
前向きな意思決定を支える3つの視点
私たちは、「決断の質」を高めるうえで、大切にしたい3つの視点があります。
1. 目的を明確にする
「何のために決めるのか」が曖昧だと、判断はブレます。個人でも、チームでも、まず“目的”を言語化することが出発点です。
2. 選択肢を整理する
情報を集め、優先順位をつけ、リスクを見極めて選択肢を作る。このプロセスがあれば、迷いが減り、冷静に判断できるようになります。
3. 決めたことを実行する
最後は「行動に移すこと」です。行動を前提とした意思決定こそが、組織を動かします。
どんな職種・階層でも活きる「決める力」
このような考え方は、管理職だけでなく、若手社員や現場リーダーにも有効です。どんな立場でも、「自分で考えて、動ける人」が増えれば、組織は確実に変わります。
また、判断力の強化は、単なる業務改善だけでなく、部下育成やチームマネジメント、顧客対応の質向上にもつながります。
決断の仕組みを、自社らしく育てたいと考える皆様へ
私たちは、この考え方に共感いただいた企業様とともに、**その組織やチームの現状に合わせた「決める力を育てる研修・ワークショップ」**を共創しています。
たとえば
若手社員に「自分の頭で考え、動く」経験をさせたい
中堅社員に「納得感のある判断基準」を身につけさせたい
管理職同士の合意形成や決断の質を高めたい
そんな課題感をお持ちであれば、ぜひ一度、貴社に合った形を一緒に考えてみませんか?
決断力は、組織の文化をつくる力です。「この内容、うちの会社にも必要かも」と思っていただけたなら、まずはカスタマイズ研修などお気軽にご相談ください。


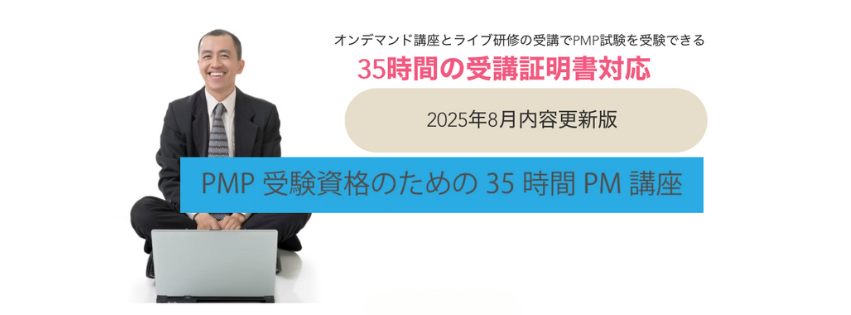


コメント